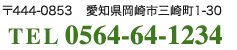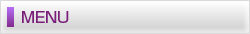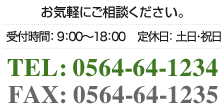‘民事再生’ カテゴリー一覧
民事再生手続後の自分の財産について
Q. 民事再生の場合、持っている財産はどうなりますか。
A.
民事再生の場合、債権者への支払総額を算定するにあたり、所有資産総額を計算する必要があります。その金額を証明するための資料を裁判所に提出する必要がありますが、基本的には処分までする必要はありません。
よくある主な財産は以下のとおりです。
- 預貯金・積立金
通帳や定期預金の証書の写しを提出しますが、解約する必要はありません。 - 生命保険
保険証書や解約返戻金の証明書を裁判所に提出する必要がありますが、解約する必要はありません。証明書は保険会社から取り寄せます。 - 自動車・オートバイ
時価評価額の証明書を裁判所に提出する必要がありますが、売却する必要はありません。ただし、所有権留保(所有権が販売会社などに留保されている場合)がついている場合には所有権者に返還する必要があります。返還したくない場合には、申立人の代わりに払ってくれる人に債務引受をしてもらい、代わりにローンを支払ってもらうことで返還しなくても良いことがあります(債権者兼所有者が承諾する必要があります)。 - 不動産
時価評価額から抵当権などの被担保債権額を引いた金額が評価額となります。登記簿謄本や不動産業者の査定書などを提出しますが、売却する必要はありません。 - 退職金
申立時点での退職金見込額の証明書・計算書を提出しますが、前借りする必要はありませんし、もちろん本当に退職する必要もありません。証明書・計算書は勤務先から入手します。 - ゴルフ会員権・株券
時価評価額の証明書を提出しますが、売却する必要ありません。証明書は管理会社や証券会社から入手します。
民事再生による家族への影響
Q. 民事再生手続を利用した場合の家族や子どもへの影響はありますか?
A.
法律上の影響はありません。家族であっても、法律上は別人格ですので、連帯保証等していない限り、一人の借金を他の家族が返済する義務はありません。戸籍や住民票にも影響はありません。
ただし、連帯保証等している場合には影響がありますので、連帯保証人についても民事再生や破産などの対応を検討する必要があります。
また、民事再生を申し立てたことにより、申し立てた人は新たなローンが組めなくなりますので、学資ローンが組めなかったり、家族や子どもが借入をしたりアパートを借りる際の連帯保証人になれない、といった事実上の影響はあります。
民事再生にデメリットはあるか
Q. 民事再生のデメリットはありますか?
A.
事故情報(いわゆるブラックリスト)として載りますので、しばらくは借り入れをしたり、新しくローンを組んだり、クレジットカードを持とうとしても審査で落ちてしまいます。
しかし、事故情報として載るのは自己破産でも民事再生でも同様です。
現時点で支払を延滞している場合には、既に事故情報として載ってしまっている可能性が高いと思われますので、デメリットとしては大きくありません。
また、約5年の年数が経つと事故情報も消え、再び審査に通るようになると言われています。もちろん、借り入れをしない生活が一番ですので、3年の再生期間中に生活を立て直しましょう。
民事再生の申立てについて
Q. 自分で申立てができますか?
A.
もちろん、本人でも申立てできます。
しかし、申立書類の作成や複雑な計算を伴う再生計画案の作成をしなければならないほか、本人で申立てをする場合には民事再生委員が選任されますので、再生委員の報酬として、申立ての際に予納金(15万~25万円)が別途必要になります。
弁護士から申立ての場合は、上記の複雑な手続は弁護士が行い、原則として再生委員の選任もされません。また、弁護士がすぐに債権者へ受任通知を出して、本人に対する取立てを止めます。ですので、弁護士を選任したほうが、精神的なことやあらゆる面で楽に進められます。
民事再生の種類
Q. 民事再生には、どのような種類がありますか。
A.
①小規模個人再生
②給与所得者等再生
上記の2種類があります。また、それぞれに住宅資金特別条項を利用できますので、住宅ローンを別枠として支払い、自宅を残すことができます。
①小規模個人再生
再生計画案(大幅カットした残額をどのように返済していくかの計画)について債権者の議決が必要で、債権者の過半数が反対すると再生手続きは破産手続きに移行してしまいます。
しかし、債権者としては破産されるより民事再生で少しでも返してもらった方が得なので、反対されることはほとんどありません。
②給与所得者等再生
債権者の議決は不要ですので、破産手続に移行することはありませんが、可処分所得の2年分以上の金額を3年かけて支払わなければなりませんので、返済総額は小規模個人再生よりも多くなってしまう場合が多いです。
民事再生手続きについて
Q. 民事再生とはどういった手続きですか。
A.
借金の総額の一部を分割で返済していく債務整理方法です。
(1)下の表の右欄の金額
(2)100万円
(3)所有資産総額
のうちで、最も高い金額を3年(やむ得ない事由がある場合は5年)かけて支払えば、残りの負債を返済しなくてよくなる制度です。
これには小規模個人再生や給与所得者等再生の2種類があります。
また、住宅資金特別条項を利用すれば、住宅ローンは別枠として払い続けることで住宅を手放さなくてもよくなります。但し、住宅ローンも延滞している場合には、支払期間を延長してもらうなど住宅ローン会社との交渉が別途必要となります。
なお、民事再生は負債総額が5000万円以下の場合に利用できます。
| 負債額が | 1,500万円以下の場合 | 20% |
|---|---|---|
| 1,500万円~3,000万円以下の場合 | 300万円 | |
| 3,000万円~5,000万円以下の場合 | 10% |